こんにちは、皆さん!「奇跡の人」は1962年のアメリカ映画。ヘレン・ケラーと、その教師アン・サリバンを描いた感動の名作です。ヘレン・ケラーと言えば、幼くして熱病のため、目・耳・口が不自由にもかかわらず、その三重苦を乗り越え、高等学問を修め、福祉活動に生涯を捧げた偉人ですね。
ヘレン・ケラーの少女時代、触感だけに依存し訳も分からずわがまま放題に振る舞うヘレンに躾と教育を施したのは教師・アン・サリバン先生でした。本作は、サリバン先生の厳しくも熱い指導の下、ヘレン・ケラーが言葉や物事の意味を始めて認知し、新しい世界が開ける瞬間を描いた感動の物語です。
まさに、熱意と精神力と努力の賜物、今に通じる「ミラクルワーカー=奇跡の仕事人」に共感し尊敬の念止みません。
「奇跡の人」予備情報
「奇跡の人」は、1962年のアメリカ映画(英題:The Miracle Worker)。幼児期に熱病のため目・耳・口が不自由となり三重苦を背負い育った少女ヘレン・ケラーと、その教師アン・サリバンの物語。
自らも目が不自由にもかかわらず、不屈の精神をもってヘレン・ケラーに指文字で言葉を教え、新しい世界を開かせる感動のヒューマン・ドラマ、アカデミー賞受賞作品です。
【スタッフ】
監督:アーサー・ペン
脚本:ウィリアム・ギブスン
原作:ウィリアム・ギブスン
【キャスト】
アン・バンクロフト、パティ・デューク他
「奇跡の人」ざっくりあらすじ
生後まだ2歳に満たないヘレンは熱病に侵され、聴力、視力、言葉まで失ってしまいます。教育を受けることもままならず、ヘレンは触覚だけを頼りに育ち、粗暴でわがままな娘に育っていました。
このままではいけないと、両親はヘレンへの躾けと教育のため、住み込みの家庭教師を雇うことにしました。
そしてやって来たのが、盲学校を卒業したばかりの若い女性、アン・サリバン先生です。彼女は自身が盲目でしたが手術で視覚を取り戻したばかり、強い精神力を持ちヘレンを教育する熱意に燃える人材でした。
食事の席で傍若無人に振る舞うヘレンにサリバンは驚きますが、ヘレンの将来のために徹底的に躾けと教育を施す必要性を強く感じるのでした。
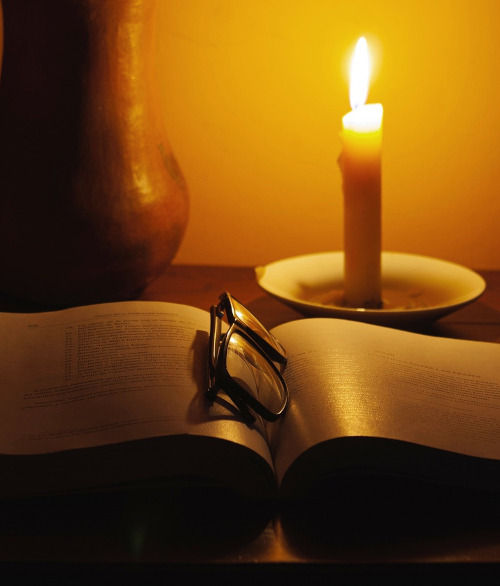
日々ヘレンと悪戦苦闘するサリバンでしたが、やがてヘレンの聡明さに気づきます。手指でアルファベットの形を教えると次々に全てマスターしてしまうのです。
しかし、それは文字を理解したのではなく単なる遊びとしか捉えていなかったのです。
家族がヘレンを憐れんで甘やかすため、サリバンは思い通りヘレンを躾けることができません。サリバンは二週間と期限を切り、離れの別棟にヘレンと二人だけで暮らすことを提案します。
そこでサリバンは厳しく躾けようとしますが、ヘレンは意地になって反抗、その強情さに思い知らされます。しかし、約束の二週間が終わる頃、サリバンの執念が実を結び、ヘレンは衣服の着替えを自分で行い、フォークでまともに食事をすることができるようになっていました。
両親はヘレンの大きな変化に大満足してヘレンを家に戻すつもりでしたが、しかしサリバンは、アルファベットの文字の持つ意味を理解できないままのヘレンには更なる教育が必要だと考えます。
甘えさせてくれる親元へ戻ると、ヘレンは元のように傍若無人に振る舞い出します。サリバンはそんなヘレンを捕まえると外へ引きずり出し、井戸で水差しに水を汲ませようと揉み合います。
この時、ヘレンにある変化が訪れます。冷たい水がヘレンの感覚を目覚めさせたのでしょうか、ヘレンはサリバンの手を取り、指でWATERと綴ったのです。次々に物を触り、物に名前があることを知り、アルファベットの形は、それらを表す記号であることを知ったのです。
サリバンの情熱と努力が実り、ついにヘレンは文字の現す意味を理解し、言葉があることに気が付いたのです!
「奇跡の人」見どころ・感じどころ

◆二人の「奇跡の人」
原題はミラクルワーカー(The Miracle Worker)、つまり奇跡の人とはサリバン先生のことを指しています。三重苦を背負った少女に躾や教育を施すことは並々ならぬ熱意と努力が必要だったことでしょう。困難な仕事を成し遂げたアン・サリバン先生は、まさに奇跡の仕事人、その偉業は讃えられるべき地上の星の一つですね。
同時に、不自由な目・耳・口と三重苦を克服し、サリバン先生の熱意と努力に応えて社会福祉に献身したヘレン・ケラーの生涯もまた奇跡の人と讃えられるものでしょう。
三重苦の少女に指文字で言葉を教え、新しい世界を開かせるまでを描いたヒューマン・ドラマ、感動です!
◆ヘレン・ケラーの生涯
ヘレン・ケラー(1880~1968):生後1歳半の頃、病を得て高熱で失明、耳も聞こえなくなり、声や言葉も失い3重苦となり、家族のことも世の中のことも全く理解をすることなく育っていきました。
7歳の時にサリバン先生と出会い、厳しく躾けられ、指文字でやっと言葉の認知が始まり、意思の疎通が出来るようになりました。
その後、盲学校や聾(ろう)学校に学び、ラドクリフ・カレッジ(現ハーバード大学)に入学。卒業後は障害者の教育や福祉のため働き、日本を含め世界各地を歴訪、生涯をその活動に捧げました。著書に 「わたしの生涯」「わたしの宗教」 など。
◆アン・サリバンの生涯
アン・サリバン(1866~1936):幼児期、病気で視覚障害者となり、9歳の時には母親が亡くなり、足が不自由だった弟と共に施設に入るも、ほどなくして弟は亡くなってしまいます。14歳の時、パーキンス盲学校に入校し指文字を学びます。複数回の手術を受け、完全とはいかないまでも視力を回復することができ視覚障害者のために働き始めます。
20歳の時にヘレン・ケラーの家庭教師となり、以後、ヘレン・ケラーを支え続け、70歳でその生涯を閉じました。
「奇跡の人」ミラクルワーカー!

実話 ミラクルワーカー
映画「奇跡の人」(原題:The Miracle Worker)は、ヘレン・ケラーとその教師アン・サリバンの実話をもとにした作品です。
目も見えない、耳も聞こえない、言葉の意味も分からない、そんな子供の躾けや教育は途方もなく困難な道だったことでしょう。三重苦を背負い、言葉を持たない少女への教育、誰もがこの困難な仕事を諦め匙を投げました。
しかし、アン・サリバン先生は、その熱意をもって彼女のために新世界の扉をこじ開けたのです。仕事とはいえ、この難題をやり遂げたサリバン先生こそ奇跡の人、奇跡の仕事人、ミラクルワーカーなのです。
彼女の強い精神力と終わることのない努力は、奇跡という言葉だけでは語りきれない価値があるものだと思えますね。
奇跡の仕事人
「奇跡の仕事人=ミラクルワーカー」という概念は、現代にも通じています。例えば、救急救命医師や弱者を助け希望をもたらす福祉職員、一流の技を極めた職人さんなど、さまざまな分野において奇跡の仕事人が存在します。彼らの持つ特別な才能は、最初から天才だったわけではなく、多くは継続的な努力と強い精神力によって生み出されたもので、人々の心を癒し、動かし、また自らの人生をも変える甲斐あるものとなっているのです。
「継続は力なり」とよく言いますね。まさにその通りです。奇跡を起こす人々に共通するのは、諦めない心と積み重ねた時間です。自分のことだけでなく、サリバン先生のように、熱い憐憫の情を持ち、他者の可能性を信じて、手を差し伸べる姿勢は、現在のボランティア精神にも通ずる尊い行いですね。
私たちの周囲にも、私たちを感動させてくれる「奇跡の仕事人」はたくさんいるようです。映画やTVドラマに見る派手な劇様にだけあるのではなく、静かな献身と、地道な努力の中にこそ、真の奇跡は宿っているのだと思われます。
◆ ◆ ◆
「奇跡の人」まとめ
はい、身体の三重苦にも負けず、大学まで進学し、福祉活動家として人生を歩んだ偉人ヘレン・ケラーと、彼女を目覚めさせ、教育を施し導いたサリバン先生の信念と努力の感動物語でした。
原題はミラクルワーカー、映画ではサリバン先生のことを指しますが、私たちの周りにも専門職や職人さんなど様々な仕事において奇跡の仕事人がたくさん存在していますね。強い精神力と努力の賜物・・継続は力なりです!
古い映画ですが、人生で必ず観ておきたい映画の一本です。

★それでは、またお会いしましょう。Good Luck!














